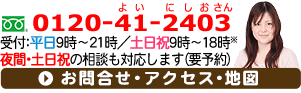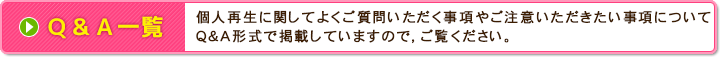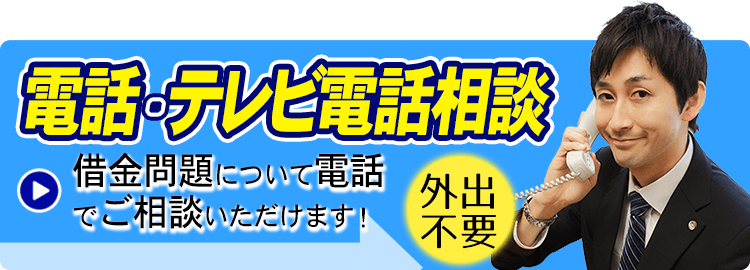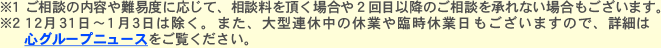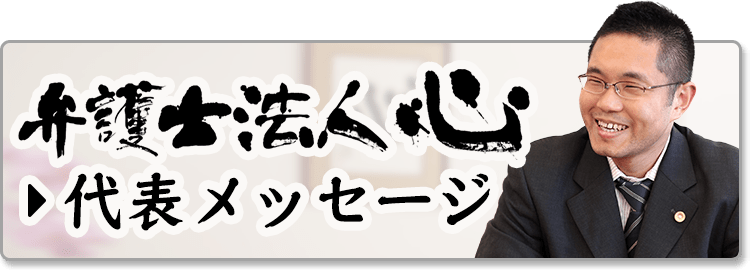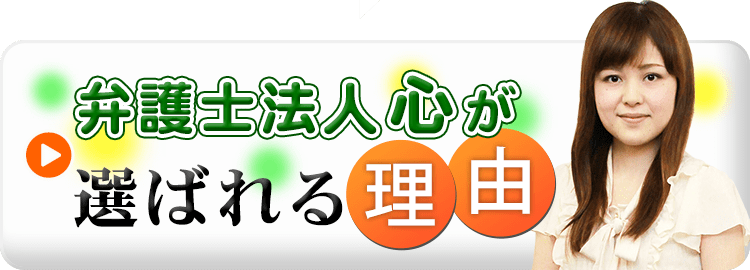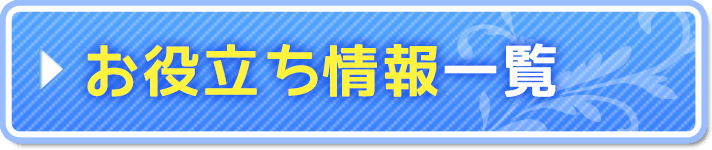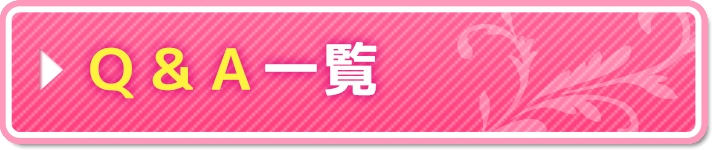お役立ち情報
個人再生に失敗するケース
1 依頼後の状況によっては個人再生ができなくなることもある
一般的に、個人再生を弁護士に依頼してから、再生計画が認可されるまでは数か月~1年半程度の時間を要します。
相談・依頼時点では個人再生ができる見込みであったものの、個人再生申立ての準備段階における不備や、申立て後の財産等の状況変化によっては、個人再生ができなくなることもあります。
以下、代表的なケースについて説明します。
2 資料収集や弁護士費用の支払いができないケース
個人再生は、裁判所への申し立てを行う前に、多くの資料の収集や書類の作成が必要とされます。
代表的なものとして、数か月分の家計表、すべての預貯金通帳の過去数年分の写し、源泉徴収票、課税証明書、退職金見込額計算書、不動産の登記と査定書、保険証券と解約返戻金計算書が挙げられます。
このなかには、債務者の方が作成、取得しなければならないものも多く含まれます。
必要な時期までに資料を揃えられない場合、申立てをすること自体ができません。
また、個人再生の弁護士費用は、毎月積立てる方式(いわゆる分割払い)とすることが多いです。
収支の管理がしっかりとできず、積立てができない月が発生してしまうと、弁護士が辞任せざるを得なくなることもあります。
3 申立て後に返済原資が下がってしまったケース
個人再生をすると債務総額を大幅に減額することができる可能性がありますが、減額後の債務を分割返済していく必要もあります。
再生計画認可後の想定返済額を確保できるだけの収入を、継続的に得られる見込みがあることが前提となります。
しかし、申立て後に勤務先の倒産やリストラ、病気・ケガなどによって収入が大きく下がってしまうと、再生計画どおりに支払いを継続することが困難になります。
このような場合、自己破産に方針変更をすることもあります。
4 清算価値が想定以上に大きくなったケース
個人再生には、清算価値保障原則というルールが存在します。
これは、債務者の方が保有している財産(不動産や自動車、保険、預貯金など)の評価額以上の金額を返済しなければならないというものです。
申立ての準備段階においては、ある程度の資産価値を見積もって計画を立てますが、その後評価額が想定以上に高くなる場合があります。
たとえば、不動産の相場が上昇するということが考えられます。
このような場合、清算価値が大幅に上昇し、再生計画認可後の想定返済額も大幅に増えてしまう可能性があります。
収入の中からでは返済が困難と言える場合、自己破産を検討することになります。
小規模個人再生と給与所得者等再生 住宅資金特別条項を利用できない場合